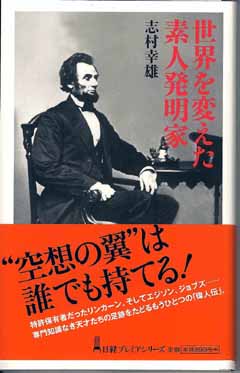 �@�@
�@�@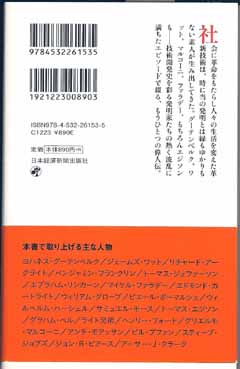 �@
�@
���u���K�Y�i�O�����ԑ���j�̔����ƃV���[�Y��O�e
�@�@
�@
���l�G�E�u���k��v���Ƃ̑Θb�E�u���@�K�Y
�@���N�͏��a10�N���܂�̎��������u����v���}����ߖڂ̔N�ł���B���U�t�̖{�������Ă������]�g���i�ԑ��\������j�A�㓡�c���q�i�ԑ��s�������c��j���N�̖��O�����������A�F�������Ԃł���B�q���̍�����u�l��50�N�v�ȂǂƋ������Ă������ゾ���ɁA�v�������Ȃ������̉��b�ɗ����Ă���킯�����A���������Ă������������т�Ă����Ƃ����̂��������B
�@������ƌ����ׂ����A����̐l����u����ȍɂ͌����܂���ˁv�Ȃǂƌ�����ƁA���ʂ��Ȃ��������Ȃ�B���ŋ߂����������̒����i�N���̈ӂɔj�ԑg�u�c���y���v�ɏo�������ہA�i����œ��k��V���[�Y�̖���Ƃ̍O�����j���瓯���悤�Ȍ��t�Ղ����B�O������͎�������Ⴂ�A�����ʂ�̒c�ゾ����A�䂪���̗͖ڂɌ����Ă���B�@����ɁA�����w�̐�y�Ǝ����グ�Ă��܂������߂́A�ꂵ����̔����������̂ł͂Ȃ����B
�@�Ⴓ�̈ێ���ňӌ�����v�����̂́A�Ώۂ̂�������킸�u�D��S�����������邱�Ɓv�������B�����Ŋ��������āA�O�����ӂ̉��y�k�`�ɂȂ�A�����p�������Ȃ��珉�߂Ĕ������k�o���R�[�h�₻�̌�̎��W����b���H�ڂɂȂ����B���Ȃ݂ɁA�ŏ��̈ꖇ�́A�����݂Ȃ���h���H���U�[�N�́u�V���E���v�B������40�N�߂��O�A���̃v���n�ŃA���`�F���w���A�`�F�R�t�B���̉��t���������A�ڔ����ʂ�̃��R�[�h�V���b�v�ŒT���o�������̂��B
�@�ԑg���ł��̉��t�Ɏ����X���Ȃ���A�W���P�b�g�̎�����f�U�C���������̋��Y���炵�����邩��ɂ��e���Ȃ��Ƃ��b��ɂȂ����B�����A�u���ꂱ���������l���̋M�d�ȕv�Ƃ��������O������ɉ��y���D�Ƃ炵���S�̗D�������o�����B�i�Z�p�]�_�Ɓj
���l�G�E�u�X�N�X�l�s���v�E�u���@�K�Y
�@���炪���Z�V���ǂ̒��ԁA�˖���j�N���P�ʉ��i�̃R�����u�ĘF�~��v�̏����o���Ɂu�N�X�X�ԑ�������A�X�N�X�l�������炸�v�Ə����Ă��瑁���������I�ȏオ�o�B���n�i�H�j�̔ނȂ�ł͂̈��p��ŁA�����͂����P����������Ȃ��������A�������ғ��肵�������ł́A�������ɐg�ɟ��݂Ċ��������Ă���B���̂P�N�Ɍ����Ă����l���̐�y�E�F�l���S�Ђɓ������B
�@�O�c��������B�N�͂P�ゾ����w�̓������ƂŁA�h�C�c�ꎫ���̏o�ŎЁA�O�C�Ђ̎В������߂��B���{�N��c����Ȃǂ��o��������ނŁA�o�Œc�̂̓��{���Џo�ŋ���ł͍Ĕ̐��x�ێ��ŋ��ɓ������B
�@���ʐ�����B�o�D�ɂ��Ė�������Ǐ��ƁB�u�b�N�t�F�A�̃��C���s���u���{����R���N�[���W�v�̐R���ψ��������肢���ĂU�N�قǂ����b�ɂȂ����B�R�N�O�ɂP�N���̎����������������������ƁA�u���̕��������Ǝv���Ă����̂Ɂv�Ɖ�����ꂽ�̂��Ō�̉�b�ɂȂ����B
�@�c������B���d���Ȋw�̐��E�I���ЂŁA���叕�������ォ������ɂ킽�邨�t�����������Ă����B�_�����������d���̔����ł̓m�[�x���܌��ɋ[����ꂽ���A���͂����Ɛ�́u�������v�ɂ������B87�N�W���A���o����ʂ̘A�ځu���d���̃C���p�N�g�v���������M�����̂��A���͐̂̎v���o�ɂȂ����B
�@���c�����ꂳ��B�V�����L���̃G���N�g���j�N�X�f�ރ��[�J�[�A�i�~�b�N�X�̉�ŁA���̓h����Ђ𐢊E�e�n�Ɏ��Ə��������O���[�o����ƂɈ�ďグ���B11�����{�̂��ʂ�̉�ł͂h�b�t���ォ��̃W���Y�o���h���Ԃ��S�D�����̐l�𓉂ޒ��ׂ������߂đt�ł��B�i�Z�p�]�_�Ɓj
���l�G�E�����ԑ���̂��ƁE�u���@�K�Y
�@10��13���ɂ́A�n�����琅�J�s������o�Ȃ��ē����ԑ����J�����B���a53�i�P�X�V�W�j�N�ɔ������Ă���̂�33�N�̗��j�������ƂɂȂ邪�A�r���łP�x�x��ł��邩��A���N��32��ڂɂȂ�B
�@�g�D�ł���ȏ�A�������Ή����������邪�A����ɓo�^����Ă����������P�R�O�O���ƕ����Ό��\�����Ǝv����ɈႢ�Ȃ��B��������ł́A���ۂ̐����䂤�ɂ��̂Q�{�ȏ�ɒB����Ƃ̌��������邩��A�z��O�̐l���ƌ��킴������Ȃ��B���̂��Ƃ��A�����ԑ��̐l���������ۂ̈������ɂȂ��Ă���Ƃ͎v�������Ȃ����A�܂��������W�Ƃ����E�\�ɂȂ낤�B
�@�����Ƃ��A������i�́A��ɂ���悤�ɖԑ��o�g�҂Ɍ���Ȃ��B�ԑ�����芪�����ӎs�����̏o�g�҂ł��悯��A�����A�E���Ȃlj��炩�̌`�Ŗԑ��ɂ䂩��̂���l�ł����܂�Ȃ��B������ӊO�Ȑl������ɂȂ��Ă��āA�v��ʏo����������肷��̂��A���̉�ɎQ�������蓾�ł���B
�@�ԑ���̓��ٌ��ۂƎv���邱�ƂɁA�������w�ȗ��̒ʊw��悪���Ȃ�L��ɂ킽���Ă������Ƃ������āA���̂ӂ邳�Ɖ�Əd������������������Ƃ��B���͈̔͂����A�Η��A�����ՁA�����ʁA���y�A��C�A���C�ԂȂǂɋy�сA���葤�̂ӂ邳�Ɖ�̉�ɂȂ��Ă���l�����Ȃ��Ȃ��B
�@�����ԑ���͔N�ɂP�x�W�܂��Ėԑ��ݏZ�̍����������ނ̂��ʂ葊�ꂾ���A�ӎ�����ɂ��悵�Ȃ��ɂ���A�����u�ԑ�������`�v�̂悤�Ȃ��̂��\�o����̂���ŁA�����������ɂ��ԑ��I�Ȃ̂ł���B�i�Z�p�]�_�Ɓj
���l�G�E����w��v�o���L�E�u���@�K�Y
�@�m�g�j�����u����w��v�ɏo�����邱�ƂɂȂ��ăr�f�I�B�肪�������B
�@�e�[�}�́A�m�[�x���܂̃p���f�B�[�A���m�[�x���܂ȂǂƂ����Ėډ��l�C�㏸���i�H�j�́u�C�O�E�m�[�x���܁v�B�X��30�����{�N�x�̎�ܔ��\���Ƃ����āA����ɐ�삯�ĂQ�T�A���̃X�y�V�����œ��܂́u�l���킹�A�����čl��������v�����ɔ���̂��_���ł���B
�@�o���҂ɂ͌���|��@�u�o�E�����K���v�̔����ҁA��؏����������{�l��҂R�l�Ǝ����u�搶�v�Ƃ��ĎQ�����A�u���k�v�̔��Ζ���ɏW�@���N��Ǝ��R�z���̓��_��W�J����Ƃ������́B
�@���̓��e�͂��Ēu���Ƃ��āA���̔ԑg����������������A�w��̐��E�ɂ͏펯����E������ʔ������Ƃ������悤�Ɠw�͂��Ă���l�������������݂��A���̗V�ѐS���m�I�T���S�̌���⌤���̈�̊g���ɂȂ����Ă���Ɠ��S�����̂ł͂Ȃ����B������܌��ɋ����������ۂ̌����҂́A���Ɛ��E������U��l�̃E���`���W�߁A���̃f�[�^�x�[�X�����d���ɂ��Ă���B
�@������n�́A���{�́u���v�̒��_�ɂ��鑾�c���N��ƁA�܂��������n�[�T���Ȃ��ɃT�C�G���X�����݂�����̗v�f����p��_���A���ꎩ�̂����ȗ��ꌻ�ۂ̎��~�߂ɂȂ�Ƃ������c�_���ł������Ƃ��B�ނ�̂����Ȃ�ʉȊw���_�Ɍh�ӂ�\�������B
�@�]�v�Ȃ��Ƃ����A�������͂X��22�A29���i�j��10��55���ŁA���͂Q��ڂɏo���B�i�Z�p�]�_�Ɓj
���l�G�E���܂��܂́u�I����L�v�E�u���@�K�Y
�@�W�����}���邽�тɐ펞���i��������m�푈�́j�̋L�^����L�ނ�ǂޏՓ��ɂ�����̂́A�풆���q�����炾�낤���B
�@�茳�ɂ��鍂�����u�s����L�v���J���ƁA�W��15���̍��Ɂu�V������ł͂ǂ�������s�B���̍s�͉̂����V���������Ă������A�V�����������������҂͈�l���Ȃ��v�Ƃ���A�i��ו��u�f��������v�ł́u�x��̏j����F�X�����ĐQ�ɏA���ʁv�ƒ��߂������Ă���B
�@�s��̎~�ߕ��͐l�Əꏊ�ɂ���Ă��܂��܂����A���������^�C���}�V���ɂ��������悤�Ɉ�C�ɂ��̓��Ɍ�߂肵�Ă��܂��̂́A���ꂾ���Ռ��x���傫����������ɈႢ�Ȃ��B
�@��Ƃ��������悤�Ȃ��̂Ƃ͌����������Ⴄ���A���̕��������悤�ȋL�^���c���Ă��邱�Ƃ��u�ԑ���P�̋L�^�v�i�ԑ���P�̔茚���ψ���ҁj�Œm�����B���c���̎��̎����͐��U�����E�ɕA�I�펞�ɂ͈�x�������w�Z�ɍݐE���Ă����B�Ƃ��낪�A�{���ʁi�H�j�Ȑ��i�̂����炵�ނ�Ƃ��납�A�Z���E�߂Ȃ���A�ӊO�ɂ��Ȗ������ȁu�w�Z�����v���c���Ă����B
�@�����̊W�ŏI��̓��̊j�S�������������p����ƁA�u���߁A�V�c�É��̏d���������B�c���a�̎���̕����ɂāA����䩑R�A�����ʁB�闈�Z�ґ����v�Ƃ���B
�@�Z�����͂����A���̋����Ƃ��ČR����`����ɐg������Đs�����Ă����I���W�̐S��}�炸���f�I����Ă���悤�Ɏv���B
�i�Z�p�]�_�Ɓj
���l�G�E�f��ك[���Ɏv���E�u���@�K�Y
�@���̎��ʂɂ���u�v���U�v�������Ă��Ďv���̂́A�ԑ��̕������������̒n���s�s�ɔ�ׂĂ���ϊ����Ȃ��Ƃ��B�G�R�[�Z���^�[�����́i�H�j�������������́u�g�̏�m�炸�̃n�R���v�Ƃ������ᔻ���������悤�����A�ǂ����Ăǂ����āA���̖k�ӓs�s�́u�������u�v�Ƃ��ď\�ɋ@�\���Ă���悤�Ɏv���B�@���̖ԑ��ɂ��ĉf��ق��F���Ƃ����̂́A�����ɂ���Ȃ��B�������Z�����������a30�N�O��ɂ́A�f��ق��R�A���|�فi����Ȗ��O�������j���P�A���킹�ĂS���������̂�����A������l����������Ƃ������f�B�A�̕��y�Ƃ������O�I���������Ă��Ă��������傫�߂���B�@����A���Z����̓���������āA����Ȃ��Ƃ��b��ɂȂ����ہA�u�f����ς����Ȃ�����k���ɍs���v�Ƃ����b�����B������P�֖̕@�ɈႢ�Ȃ����A�{���s�s��Ԃɂ����镶���I���l�̏[���x�́A��C���z���Ƃ��������ނ̂Ɏ��Ă��āA�g�߂ȏꏊ�ŘJ�������Ė��킦�邱�Ƃɂ���B���̌������݂��݂�������Ă��܂��ẮA�ɒ[�Șb�A�s�s�@�\�̕����ɂ��Ȃ��肩�˂Ȃ��B�@�������N���O�̘b�����A������w����ɒʂ����w���X�̉f��ق��ق̕��j��ł��o�����B����Ɗw�������������オ���āu�ٔ��Ή^���v��W�J���A�َ���O����P���B
�@�����̋���́A���Əꍇ�ɂ���ē��������̂ł��邱�Ƃ������Ă���B
�i�Z�p�]�_�Ɓj
���l�G�E�n�����̌��p�E�u���@�K�Y
�@�I�z�[�c�N�ӂ邳�ƘA����Ȃǂ̏�ł����܂������邱�Ƃ̈�Ɂu�ԑ��ɂ͒n����������v�Ƃ������Ƃ�����B�l�����Ɋ������ꌻ�ۂ��d�Ȃ��āA����k���ȂǂɌ��炸���{�S�y�̒����s�s����u�n�����v�����ł����邱�Ƃ��l����ƁA���̎����͖ԑ��ɂƂ��ē���������Y�ƌ����ׂ����낤�B
�@������n����������̗]���������ʏI�풼��Ƃ����̂����猩�グ�����̂��B�ԑ��V���n�ƎҁA�����v�����琶�O�Ɍb�����ꂽ�w�킪���U�ɉ��Ȃ��x�ɂ��A�s���{�s�̏��a22�N�A�w�Ǖ����̐����p���s���Ƃ����������������̂��́A�u�ǂ̐��}�ɂ��킸��͂���鎖�Ȃ�����ɂ����т��x�M�ɂ����������V�ɂ��Ė��N�ȐV������Ƃ��v�Ӑ}���đn�������ӂ���Ă���B���̎u��s�ɂ��āA�����������u���ł���B
�@�����ɂ킽�邪�A���Z����ɐV���ǂ̒��ԂƐ��삵���u�ԑ��샖�u���Z�V���v���S���R���N�[���ŏ�ʓ��܂��ʂ������̂��A�n���V���Ђ�����������̐��ʂ������B�������������ɐV���Ђ̌���ɏo�����đg�ł�Z����Ƃɂ�����������Ƃ́A�����g�̂��̌�̐E�ƑI�����܂߂āA�����̌��ɂȂ����B�w�Z�V���̕ҏW�����߂����ē����̓c���Z���Ƃ�荇�����̂��A���ƂȂ��Ă͉��������v���o�ł���B����Ȍ��C�Ȓ��Ԃ̈�l�ɑ�����O�s���������B
�@�ԑ��V�����|�����n�����̓`���͍����A�ԑ��^�C���Y���Ɍp������A���S�ȃW���[�i���Y�����_�����Ă���悤�Ɏv����B�n�������琬�̃I�s�j�I�����[�_�[�Ƃ��Ă̌��������҂������B
�i�Z�p�]�_�Ɓj
���l�G�E�k�ӓs�s�̕������E�u���K�Y
�@�ԑ��o�g�҂͎��܁A�����������s�I�Ɂu�����ʂ�n�v�Ƃ�����������������B�����A������A�����Z��Ƃ�����������ȕ����͂Ƃ������A���̓y�n�Ȃ�ł͂̌ŗL�œy���I�ȕ����́A�ނ��낵�����荪�t���Ă���A�Ǝ��͍l���Ă���B
�@�O�������y�����ق�����L�˂ɑ�\�����k�������͂��Ƃ��A�ߔN�̗��X�܂�A���̉w�Ɏ���܂ŁA���̎��̂͂Ȃ��Ȃ����ʂʼn��s�����[���B
�@���s���̐[���Ƃ����A�ŋ߂����蒸�����ԑ��s���}���ي��s�́u�ԑ��̐}���قP�O�O�N���v�ɂ��ƁA���̖k�ӂ̏��s�s�ɁA����39�i�P�X�O�U�j�N�ɑ������u�ԑ��}���c�����v�Ƃ��Đ}���َ{�݂��J�݂��Ă��邱�Ƃ��B�����ł��u���I�Ȍ����I�����{�݂̒a���v�������Ƃ������猩�グ�����̂��B
�@������肩�A���̘b�ɂ́u�O�j�v�������Ė���20�N�㔼�ɂ͂��łɁu�ԑ����Њفv�Ȃ���̂����݂��Ă����炵���̂ł���B�ԑ��s�j�̕Ғ��҂Ŗԑ��n���j�������c���������c���ŏ��������a50�i�P�X�V�T�j�N�P���T���t�̖ԑ��V������Ŗ��炩�ɂ��Ă�����̂ŁA���̏��Њق����u�L���X�g���̓`���ɊW�����������̂ƍl������v�Ƃ����̂��B�����A���̍��̊O�������̍����ɐG���悤�Șb�ŁA�S���M���Ȃ�v���ł���B
�@������q�Љ�w�҂̓��c�����͏����O�ɏ������w���{�Ӌ��_�x�̒��ŁA���{�����Ɂu�Ӌ��v�Ƃ����⏕�����������Ƃœ��{�l�ɓ��L�Ȏv�l�̂�����������Ă���Ǝw�E���Ă���B�Ӌ��̃A�C�f���e�B�e�B�[�i��̐��j��������{�Ƃ��Ĉ�ۂɎc���Ă���B
�i�Z�p�]�_�Ɓj
���l�G�E�u�j�Փs�s�v�ԑ��E�u���K�Y
�@���{���\���镶���l�ފw�҂œ����ԑ���̗L�̓����o�[�ł���R�����j����Ɂw�j�Փs�s�x�i��g���X�j�Ƃ�������������B�s�s�̖��͂͌��ƈł���������u�j�Ր��v�ɂ���A���ꂱ�����l�Ԃ̊����ƕ����̓�����[�w�ɂ����ċK�肷��s�s�̖{���A�ƌ���B
�@�R������͂��̌��^�����a10�N�㏉�߂̖ԑ��Ɍ����o���Ă���B�o���n�͔��y�����������A���オ���̐����E�������c��ł����W�ŁA����I�ɖԑ��ɏo�����A�����J�[�̕Ћ��ɏ悹���Ē����ɎU�݂���َq��������B�ڐ��̒Ⴂ�����璭�߂��ԑ��̐S�ە��i�́A�R���N���[�g�ŊO�������R�K���Ẵr���i�m�����X���w���j�A�j�����̋u�̏�ɂ��т���~�`�h�[������n���ȉ��������������y�����فc�ȂǁA�u�ً�Ԃ̐^�����ɖ������V���������o���v��̂ɏ\���������B
�@�Ȃ��ł��A�đ����q�����{�E�̗����Ƃ���ߑS���Y�𓊂��đ��������y�����قɂ͂�������̍��ꍞ�݂悤�ŁA�u���̌����ɍs���ߓ����}�X�ȍ�ŁA���̋ߓ������ɂ��̂��邢�ɂȂ��ēo���čs���ƁA�ڂ̑O�ɓ˔@�Ƃ��Ĕ����̔����ق�������Ƃ������̏u�ԂɁA���͖�������Ă��܂����v�ƐU��Ԃ��Ă���B
�@�Ȃ�Ƃ������[���̂́A�ԑ������w�Z�i���݂̓샖�u���Z�j����A�u���̌����ɏZ�݂������Ǝv���āA�R�J���قǗF�l����ė��ݍ���Ŋْ��̕đ�����ɉ��h�����Ă�������v�����ł���B
�@����Ȍ��̌������E�I�ȕ����l�ފw�҂���ďグ���Ƃ���A�k�ӂ̒����s�s�A�ԑ��̕����C���t���͌��̂Ă����̂ł͂Ȃ��B
�i�Z�p�]�_�Ɓj
���l�G�E�菑���h�̗J�T�E�u���K�Y
�@���̌��e�������������́u�菑���h�v�ł���B�n�C�e�N����݂̎d���Ɋւ���Ă��Ȃ���A�Ȃ��p�\�R�����g��Ȃ����Ƃ悭�s�v�c�����邪�A�œK�̎��ȕ\����i�͌��e�p���̃}�X�ڂ���ЂƂ��߂Ă������ƂƏ���Ɍ��ߍ���ł���B���̐g�߂Ȑl�ł́A�m�[�x�������w��҂̍]��扗�ގ��┼���̂̐��V����k�匳�����炪�菑���h���B
�@���ȗ��𐳓�������킯�ł͂Ȃ����A���{�l�͂��Ƃ��Ǝ菑���h�������B���{��͕������̏��Ȃ��\�������̃A���t�@�x�b�g�ƈ���āA�\�ӕ����̑����������g���B���܂��Ɋ����ɂ́A�����������ƂɋN�����������ً`���肪���邽�߁A�R���s���[�^�����ւ̓]��������A�^�C�v���C�^�[�A�e���b�N�X�A���[�h�v���Z�b�T�[�Ȃǂ̕��y���x�ꂽ�B
�@�������t�ɁA������}�`��摜�Ɠ����悤�Ɏ�舵���t�@�N�V�~���╡�ʋ@�Ȃǂ͊J�����莞���������A���Ăɕ����Ȃ����y�������B���̂悤�ȃA�v���[�`�̈Ⴂ�́A���Ắu�L�[�{�[�h�����v�ɑR����u�菑�������v�Ƃ����Ă悭�A���̕����̈Ⴂ���Z�p�̂���悤��ς����B
�@�Ƃ��낪�A���̓��{�l�����܂�L�[�{�[�h�h�ɓ]�����̂́A���ɂ������ăR���s���[�^�Z�p�̐i���ɂ��u�J�i�����ϊ������Z�p�v���m���������炾�B�������A����쐬�����f�[�^�́A���ꎩ�̂Ɍ�肪�Ȃ�����A���̂܂܊����ɂ��Ă���A��������S�z�͂Ȃ��B
�@��A�Ƃ����A�O��ٍ̐e�ɂ́A�������̌���I�ȃ~�X������A���l�Ȍ��ʂɂȂ����B�������������Ȃ�̗��M��������������ŁA����͂�������Z�������邱�ƂɂȂ����B�㐶�A����Z������ׂ��ł���B�i�Z�p�]�_�Ɓj
�u���K�Y�i�O�����ԑ���j�̒���
�Ă��́E���������@�@�����ԑ���E��@�u���@�K�Y
�A�ڂɂ�������
�@����̃z�[���y�[�W�ҏW������A���e�̏[����}�邽�߉����e����A�Ƃ̖��ł���B���e�����܂邩�ǂ����͖��m�������A�������ڂ̈�Ɗ�����āA���Ɉ����x�A�P�C�O�O�O�����炢�̒Z�����o�e���邱�Ƃɂ����B�����������Ƃ���A���̃��V�̎�ł���Z�p�̂��ƂɂȂ�B���ꂵ�����̂ɂȂ�Ȃ��悤�C��t���Ȃ���A�����l���Ă��邱�Ƃ��C�̌����܂܂ɏ����Ă������肾�B
���u����̐V���i�Q�V���ځj
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���u���ԑ���̐V���i�Q�U���ځj
��N���{���̔����҂���u���K�Y�i�Z�p�W���[�i���X�g�j
�@�o�Ŗ{�̐��E�ɂ͢�����{��Ƃ����W�������������āA�傫���T�N�Z�X���̕��ƃm�E�n�E���̓�̗��ꂪ����悤���B����̒����͎��ɂƂ��ē���ڂ̔����{�����A��N�O�ɏ㈲�i���傤���j�����w������ͣ�̎���x�i���V��w�o�ʼn�j�������̕��@�_�Ɏ���u�����m�E�n�E���Ȃ̂ɑ��A����̕��͂��̂ǂ���Ƃ������Ⴄ�B�����Č����C���T�C�h���Ƃ������ƂɂȂ낤���B
�@���Ƃ�蔭���͐l�ދ��ɂ̢�m��̐��E�ŁA���ꎩ�̂���������A�������_�C�i�~�Y������݂��Ă���B���̕ӂ����Ƃ��m��I�ɏ����グ���v���W�F�N�g�w����̃T�N�Z�X�X�g�[���[�Ɏd�オ��B���������̐��E�͓����ɋ����I�ȋC�����݂Ȃ����Ă���A���߂���Ɣ����҂Ƃ��Ă̌l���ƁA�w��A���ƂȂǂ���������őΗ���m���A�ȋ^���Q��������]�I���A���Y���̐��E�ł���B�����̗��j�͢�l�Ƌ��ƍٔ��̗��j��ƌ�����䂦�B
�@���ہA���E�̔������ƌ����A�N�����G�W�\���̖��O���v�������ׁA�ނ̎O�唭���Ƃ���Ă��锒�M�d���A�~���@�A�f��̂��Ƃ�m���Ă���B�������A�{���ɂ����������Ƃ����A�ǂ̏ꍇ�ɂ���s������ގ�����������A�G�W�\���͌��Ō������������ٔ��ɔY�܂��ꂽ�B�܂������Ԃ̓h�C�c�l�Ɍ��킹��ƃx���c��1885�N�ɔ��������K�\�����G���W���Ԃ��ŏ��ƌ������ƂɂȂ邪�A���C��K�X�G���W���ԂŐ�s�����t�����X�́A���������������������Ǝ咣���ď���Ȃ��B
�@����Ƀ��b�g�Ƌ��ɎY�Ɗv���̐��i�҂Ƃ����A�[�N���C�g�́A���͖a�ы@�̔����҂Ƃ��Ē��w���ł��m���Ă��邪�A���̃}���N�X�Ɍ��킹��Ƣ���l�̔����̍ő�̓��l��i���{�_�j�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�����[���̂́A�傫�Ȕ����ɂȂ�قǁA����Ɋւ�荇�������҂������A���肪������ƃ_�B���[�}�͈���ɂ��Đ��炸�ƌ����ׂ����A��̋Z�p�A��̐��i����������ɂ͋Z�p�̐ςݏd�ˁi�����̘A�����j��قȂ�l���ɂ�铯���i�s�I�Ȕ����i�����̓������j���������Ȃ��B
�@�m�������A�v���p�e���g�i�����d���j����Ƌ���鍡���A�����̗D�挠������ٔ����\�N�푈�ɂȂ邱�Ƃ�����A��Əo�g�̌����҂��E�������̕�V���ŌÑ��̊�ƂƖ@��ő����P�[�X���������Ȃ��B�K�����͈�W���[�i���X�g�Ƃ��Đ��̋Z�p�v�V�̉Q���ɐ����A����ȏ�ʂɂ�������������Ă����B�h�b�A�F�����_�C�I�[�h�A���t�@�C�o�[�A�Y�f�@�ہA�R���s���[�^�[�A�d��ȂǁA�{���̔����߂��̏͂ɂ͎��̂���Ȏ���������������Ă���B
�@�`���ɖ{�����C���T�C�h���ƌ��������A���M�ɓ������Ď��̔O���ɂ������̂́A�Ƒn�J���̏d�v���ł���A�����������͂̌���Ƃ������_�������B���̈Ӗ��ŁA�{�������ɎႢ�Z�p�҂�w���ɓǂ܂�A���̈Ӑ}�����ݎ���Ă���������Ζ]�O�̍K���ł���B
�i�Q�O�O�U�N�X���Q�P���t�������V���Ɠ����V���Ɍf�ځj
�@�@�@�y�u���s�v��ے肷�镶���z�@�u���@�K�Y
�@ ���̒��ɂ́u�����w�v�Ɩ��O�̕t�����̂��������A�ŋߗ��s�́u���s�w�v�����̂ЂƂB�H�w�@��w�����̔����m���Y�������g����̉ʂẮu���s�w��v�܂Őݗ����ꂽ�B�������A����͋t���I�Ȍ�����������A���{�ł͂��ꂾ�����s�ɑ��鋑�۔����������A�������������Ă��Ȃ�����ł͂Ȃ��낤���B
�@�@���̍���ɂ���̂́A�u���s��p�Ƃ��镶���v�ł���B�č��̕����l�ފw�҃��[�X�E�x�l�f�B�N�g����Q����풼��ɂ܂Ƃ߂��A���{�����_�̃n�V���Ƃ������ׂ��w�e�Ɠ��x�ɂ́A���{�́u�p�̕����v�����Ắu�߂̕����v�Ƃ̑Δ�Ř_�����Ă���B�߂̕����ł́A�����̐�ΓI�ȋK������߂��A����ɔw�����Ƃ͍߂Ƃ���邪�A�����ɍ߂͜����i���j���܍߁i���傭�����j�ɂ���Čy�������B
�@�Ƃ��낪�A�p�̕����ł́A�߂��̍����͂������Ēp�����炷���ƂɂȂ�A�l�Ԃ͂��Ƃ��_�ɑ��Ă���������Ƃ����K���͂Ȃ��B
�@ ���ڂ����̂́A�x�l�f�B�N�g���p�̕����̕�������{�Љ�́u�W�c��`�v�Ƃ����ɓ��݂���u�K�w�\���v�ɋ��߂Ă��邱�Ƃ��B���{�̌����J���V�X�e���ɂ��̎�̐��x��̎�����������Ă��邱�Ƃ��l����ƁA���̍��͐[���B
�@���s��p���镶���́A�Z�p�J���̏�Ɂu���s�����������y�v���������Ă���B���s�����Ƃ��p�Ƃ��镶���́A���R�̂��ƂȂ��玸�s��ے�I�ȑ��ʂ��炵���]�����Ȃ��B���ʂƂ��āA���s���}�C�i�X�_�ŕ]������u���_��`�v������������A�u���������ʎ�`�v���͂т���B
�@ �����ЂƂ̌��O�́A����ȏ̉��Łu���s����w�ԑ̎��v����������邱�Ƃ��B���s�̊w�K���ʂ́A�ǂ����s�ɂƂǂ܂炸�������s�ɂ����҂ł���͂������A������Ӑ}�I�ɉ��������َE���Ă͓�����͉̂����Ȃ��B
�@�Ȃ����s����w�Ȃ����ɂ��āA���c�M�j���͋ߒ��w���̍��̎��s�̖{���x�̒��ŁA�u�����I�Ȍ���`�q�v�̑��݂��w�E���Ă���B���̌��ʁA���ʂ��玸�s�̌������c�_���悤�Ƃ���ƁA�g�D���Ŕ��ᎋ����A�Ǘ���Ԃɒǂ�����Ă��܂��B���ǂ́u�N���������Ƃ͎d�����Ȃ��A����������Ԃ��K�v�͂Ȃ��v�ƕ����̂��I�`�A�Ƃ����̂��B
�@ ���ǂ��́u���s�͐����̕�v�Ƃ������P����������͂������A���ꂪ�`�[�����Ă͋�O�������̖و���ɏI����Ă��܂��B
�i�Q�O�O�S�^�O�X�^�O�U�j
�@�y�]���V�X�e���̌��@�z�@�u���@�K�Y
�@�@�ŋ߂͓��{������m�[�x����҂��������ł��邪�A���͂����̌����҂̋Ɛт����{�����ŕK�����������ɕ]������Ă��Ȃ��������Ƃ��B�m�[�x�����w��܂̓c���k�ꂳ��͂��̗ǂ���ŁA��܂̕`����ꂽ���A�u�c��������āA�N�v�Ƃ��������オ�����B���ہA�Q�O�N�߂��̌��������̒��ŁA�����ł̎�ܗ��͂킸���ɓ��{���ʕ��͊w��̏���܂����������B���̋Ɛтł��鎿�ʕ��͂̐V��@�����p�I�ȑ��u�Ɏd���Ă��̂����Ẵ��[�J�[�������B���Ƃ���Ȃ��b�ł���B
�@�@����Ȃ��Ƃ��l���Ă�����A�쎌�E��ȉƂ̏����j����̃R�����i���{�o�ϐV���[���u�����ւ̘b��v�j���ڂɂ����B��ǂ���ƁA��������ɂƂ��āA���{�̉��y��ł̃A���R�[���K���͑�ς��s���̂悤�Ȃ̂��B�I�����}���Ė{���Ɋ������o�����̂Ȃ炻����ǂ����A�����łȂ��ꍇ�͂�����ׂ������������̂��{���̎p���B�u���ꂪ�ǂ��l���Ă��債�đf���炵�����Ȃ��������e�Ȃ̂ɁA�ϏO����A���R�[����J�[�e���R�[���̔��肪�苿���v�̂͐����ȕ]���Ƃ͌�����A����́u�i���{�́j�ϋq�ɕ]���̎�̐����Ȃ��v���炾�A�ƒf���Ă���B
�@�@���̖���N�́A�c������̕]���̏ꍇ�ƕ\����̂��Ȃ����̂ŁA�v����ɕ]���ґ��Ɏ�̐������@���Ă���̂ł���B�����̂������ƕ]���ł��Ȃ��̂́A�t�ɗǂ����̂�ǂ��ƕ]���ł��Ȃ��̂��B���̖{���𑨂��A�^�U���͂����肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȋw�Z�p�̐��E�ŁA����ɂ���Ȃ��Ƃ����ʂ��Ă͍��ƕS�N�̌v�ɂ��e�������˂Ȃ����ƂɂȂ�B
�@�@�S�z�Ȃ̂́A�]���̎�̐��̌��@�����{�l�����҂̋Ɛт̉ߏ��]���⎀�����ɂȂ���͂��Ȃ����Ƃ������Ƃ��B���{���\���邠�錤���҂́A�u���{�l�ł���Ȃ�����{��̘_����M�p�����A�p��Ȃ�L����v�Ƙb���Ă����B������v�����̒����ł́A�O���Z�p�𐒔q����u�m�z��`�v�ƁA�������ǂ�����u������`�v���ᔻ�̑ΏۂƂȂ������A�����̖�肾�B����ȕ������������̂��A���{�ɂ͌����̓Ƒn����j�[�N������̓I�ɕ]������V�X�e�����Ȃ�����ɈႢ�Ȃ��B
�@�@��̐��̌��@���t�a�����^�̖��ӔC�ȕ]����A���ԂɊÂ������Ђ����^�̕]���ݏo���Ă���̂��R�X������肾�B���Ƃ��ĕ����Ȋw�Ȃ̉Ȋw������⏕���͌��債�����̂���Ƃ̐R���ō̔ۂ����߂邪�A�ȑO����ꕔ������w�ւ̕肪�w�E����Ă���B���������d�g�݂{�I�ɉ��߂邱�Ƃ��\�����v�̏d�v�e�[�}�ł��邱�Ƃ��s�����ǂ�w�E�W�҂͂Ƃ��ƔF�����ׂ��ł���B
�i�Q�O�O�S�^�O�U�^�P�P�j
�@�y�����Ή��Q�O�O���~�̋����z
�@�@�F�����_�C�I�[�h�̔����҂ł��钆���C�i�ăJ���t�H���j�A��T���^�o�[�o���Z�����j�̔����Ή����߂���ٔ��ŁA�����n�ق����Ζ���̓������w�H�ƂɂQ�O�O���~�̎x�����𖽂��锻���������Ęb��ɂȂ��Ă���B���̊z���^�j��̐��������ɋ��Q�̐���^�ۗ��_���Q�������킯�����A�����҂͂����ނˁu���}�v�A�Y�ƊE�́u���f�v�Ƃ������Ƃ��납�B
�@���Ƃ�蔭���̑Ή��́A�����@�R�T���ŏ]�Ǝ҂��E����̔����̓���������ЂɈϏ������ꍇ�A�u�����̑Ή��v������ƒ�߂��Ă���B����̔����ł́A�����ɂ���ĉ�Ђ����闘�v�P�Q�O�W���~�ɔ����҂̍v���x�̂T�O�����|���ĂU�O�S���~�ƎZ�o���Ă���B���ꂪ�Q�O�O���~�ɂȂ����̂́A�������̐����z�����̊z�ɂƂǂ܂��Ă������炾�B
�@�Y�ƊE�̌��O�́A���z�̑傫�������邱�ƂȂ���A���̑Ή���������ɂȂ邩�̌������t���ɂ������Ƃɂ���B���ɍ���̔����ł́A�������̐��Y���{�i�������P�X�X�S�N����������Ԗ����̂Q�O�P�O�N�܂ł̔��㍂���P���Q�O�W�U���~�ƎZ�o�A�������ɂ��đz��z���͂����o���Ă���B
�@�{���ɂ����Ȃ̂��ۂ��́A�_�݂̂��m��ł���B�Z�p�̐��E�ł͂����ΐV�Z�p�̓o��ɂ�苌���̋Z�p�����ɂ��ċ쒀����Ă��܂��B�܂��A���͂ȃ��C�o�����[�J���o������Έ�C�ɔ���グ���������A�s�ꂩ��̓P�ނ��]�V�Ȃ������B
�@�v���x�̕]���ɂ��Ă��A����̔����ł́u�l�I�\�͂ƓƑn�I�Ȕ��z�ɂ�萢�E���̌����@�ւɐ�Đ��E�I�����𐬂��������v�Ƃ��ĂT�O���Ƒz�肵�Ă��邪�A���������҂̑������{�^�̌����J���V�X�e���ł͎���́g�~�j�q�[���h�B�ւ̔z�������ɂȂ낤�B
�@�Ƃ����킯�ō���̔����ɂ͖��_���������邪�A���{��Ƃ̌����҂̏������P�Ɉ�𓊂����Ƃ����_�ŕ]�������B
�@�����ɖR�������{�́u�Ȋw�Z�p�Ń��V��H���v�ȊO�ɓ��͂Ȃ��A���̂��߂ɂ͓Ƒn�����A�Ǝ��Z�p�̑n�o�������ő�̋����͂ƂȂ�B�������A�N������E�����ь^�̊�Ƒg�D�Ɋ���e����ł������{��Ƃ̑����́u�����E�Z�p�҂�������ʈ�������̂͂��������v�A�u�X�^�[�����҂��W�c�I�Ή��̕����厖�v�Ƃ������Œ�ϔO�����������Ă���B���̍ł��ے��I�ȁg�����h�������o�莞�Ɛ������ɒ������ɕ���ꂽ��V���z���Q���~�Ƃ����ꌏ���B
�@�Ⴂ�L�\�Ȑl�ނ��Ȋw�Z�p�̐��E�ɖ��͂������A�C���Z���e�B�u�������Č��������Ɏ��g�ނ��߂ɂ́A�Â��m���͂��ВE�������Ă��炢�����B
�i�Q�O�O�S�^�O�R�^�P�O�j
�y�V�N�̂����A�z�@
�@�����ԑ���̊F����A�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B
�@�@���{�����̌��������ł́A�s���̂ǂ��ɂ��������{�̌o�ς��悤�₭�O���ɓ������Ƃ��Ă��܂����A�n���֏o�����Ă݂܂��ƁA�s���F���܂��������ŁA�{�i�ւ̓��̂�͉����������Ǝ������Ă��܂��B�ԑ��V���̃z�[���y�[�W�Ȃǂ��猄�Ԍ���ԑ��s�̍���������A�������ɘR�ꂸ��ό������l�q�ŐS�z���Ă���܂��B
�@�@�������A���̈���ł͑��s���̖ڎw���u��������n���o�ςÂ���v���N�Ǝx���Ȃǂւ̎��g�݂Ɍ�����悤�ɁA�������i��ł���悤�ł��B����́u�ω��v���u�D�@�v�ɂ��Ȃ���A���̋ꋫ�����Џ����Ă��������������̂ł��B
�@�@�ϐg����ԑ��Ƃ����A��N�I�[�v�������u���w�����_�[�����h�v�����̐g�̉��ł��b��ɂȂ��Ă��܂��B���ŋ߁A�u��w�o�ŕ�����v�̑n���l�\���N�L�O���T�̐ȏ�Ŏ��ɂ������Ƃł����A�������N�āA�D�y�Ō��C����J�Â����ہA�킴�킴�ԑ��܂ő���L���A�Ñ��R�ɂ��邱�̐V�{�݂����w���������ł��B���͂Ƃ����Ύ��̎����i���c�K�g�j���\�N�قNjΖ����Ă����Ñ��R�����w�Z�̍Z�ɂł�����A���S���ЂƂ����ł��B�����y�n�Ƀn�C�e�N�u���ō����ő��̓d���i���[�J�[�A�f���\�[�̃e�X�g�Z���^�[�������������Ƃ��A�Z�p����݂̎d���Ɍg����Ă��鎄�ɂ͐S��h���Ԃ�����̂�����܂��B
�@�@���āA�����ԑ���ɂƂ��č��N�͑n����\���N�Ƃ����V�����ߖڂ��}���܂��B�u�ɔR�������l���̐�y�B�ɂ���ăX�^�[�g�����{����A�l�����I���o�������ł͖��O�S���̉���𐔂���Ɏ���܂����B�ԑ��Ƃ̉����͋�H�A�A���͂d���[���̎���Ɂu�ӂ邳�Ɖ�v�I�v�l�͂��������Ò��Ɖ�������������܂����A����͕ς���Ă���͂�u�ӂ邳�Ƃ͉����ɂ���Ďv�����́v�Ȃ̂ł��傤�B
�@�@���N�x�͖����ꓯ����\���N�ɂӂ��킵���Â��ɂ��悤�ƍ\�z���Ă��܂��̂ŁA�������ђn���̊W�҂̊F����ɂ͂܂������Ƃ����b�ɂȂ邩�Ƒ����܂��B��낵�����肢�\���グ�鎟��ł��B
�i�Q�O�O�S�^�O�P�^�W�j
�@�y�u�ĉ����L�v�̋��P�z�@
�@�@�u�ĉ����L�v�͖������N�A��q�g�ߒc�ɐ��s�����v�ĖM���̂Ăɂ���Ă܂Ƃ߂�ꂽ�S�P�O�O���ɏ�鉢�Ď��@���ł���B�ʓǂ���̂͏��������ւ���g���ɂ���S�T���Ŋ��s����Ă���̂ŁA�ǂ����Ǝv���ΊȒP�ɓ���ł���B���̑咘���ŋ߁A���O�̌����҂̋��͂ʼnp��A���{�|��o�ŕ����܂���܂����B�܂ɐG��ĕł��߂����Ă����ǎ҂̈�l�Ƃ��āA���̉�������т����B
�@�@��ǂ��Ċ����邱�Ƃ́A������P�R�O�N�O�̓��{�l�ɂƂ��ĉ��ď����͕����ʂ�u��斜���v�̉������������Ƃ������Ƃ��B�����A�ߑ㉻������ۑ�ɂ����ނ�́A�×~�Ȃقǂɉ��Ă̍�����Y�ƌo�ρA����@�ցA�R���g�D�ȂǂɐG��āA��i�������z�������B
���L�͂��̎g�ߒc�̂P�N�P�O�����ɂ킽�鎋�@���s�𗷒����ɋL�q���Ă��邪�A�v�Ẳs�����@�͂Ƒ씲�ȕ\���͂����܂��āA�u�����̋I�s�L�^�Ƃ��Ă͐��E�ɗ�����Ȃ��v�Ƃ܂ŕ]����Ă���B
�@�@���S����̂́A���j�w�҂Ƃ��Ă̋v�Ă��P�ɐ��̈�ɂƂǂ܂炸�A�Ȋw�Z�p�̐��E�ɓ��ݍ��݁A���̏Љ�ɑ����̎������₵�Ă��邱�Ƃ��B�{����ǂݐi�߂Ă����ƁA���Z�p�҂ł��Ȃ��Z�p�����ł��Ȃ������v�Ă��A���Ă̐�i�I�ȉȊw�Z�p��V�Y�Ƃ̓W�J�����ɐ��ׂɕ`���o���Ă��邱�ƂɋC�Â��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@���̑Ώۂ��A�����̐�[�Z�p�������d�M�@�A���C�@�ցA�S���A��s�D�͂��Ƃ��A�a�сA���S�A���D�Ȃǂ̎Y�Ƃɋy�сA����͂��A�L�^����ڂ��m���ł���B�H�i�H���K�˂ĔM�Ǘ��̉^�p�ɒ��ڂ�����A���b�g�̏��C�@�ւ��ܗg���Ȃ�����A��s�����Ƃ��ăj���[�R�����@�ւ����������Ƃ��w�E���Ă���̂́A���̂����Ⴞ�B
�@�@�@����ɋv�Ă̋����ɂ͈�т��ĈېV��ɂ�������{�̂������Ɛj�H�Ƃ�����喽�肪�h���Ă����悤���B�����h���K��̊��z�Ƃ��āA�u�ϓփn���E�m�V�Y�i�V�R�����j���A���V�e�A�����m����̓����w�e�A�ėA���X������Ӄg�X�v�Əq�ׂ���u�������{�j���e�A���ėA�o�m�r���J�J���j�n�A���j���Ӄ��i�X�R�g�ٗv�i���w�V�v�ƓI�m���挩���ɕx������t�������Ă���B
�@�@�ېV�Ƃ�������̓]����������ނɁA�����Ȃ��w�Ԃ��Ƃ͑����B
�i�Q�O�O�R�^�P�O�^�Q�W�j
�@
�y�Ȃ��u�n�C�e�N�n�R�v�Ȃ̂��z�@
�@�@�n�C�e�N���i�Ƃ����A���`�ʂ荂�Z�p�E���t�����i�����瓖�R�����v��������͂������A�����ɂ͕K���������̒ʂ�Ɏ����^��ł��Ȃ��B���{�̎Y�ƊE���\������d�@�������ݐԎ����o���Ă���̂͂��̏؍��ł���B
�@�@���R�̂ЂƂ́A�n�C�e�N���i�̑����͐����s��ł��邾���ɎQ����ƊԂ̃V�F�A�̑������������A��ʓ����E��ʐ��Y�ɂ�鉿�i�������퓅��i�Ɖ����Ă��邱�Ƃ��B���_�I�ɂ��A�ݐϐ��Y�ʂ������Ȃ�قǃR�X�g���Ⴍ�Ȃ�Ƃ����u���[�j���O�J�[�u�i�K�n�Ȑ��j���v�����̎�̑Ή��ɐ�������^���Ă���B�����Ƃ��A����Ŕ���グ���L�сA���������̗��v��������̂Ȃ炢�����A����͂��ɔȂ̂��B
�@ ���̂�����Ƃ��āA�����̗p�������~�ޗ��Ő��E�g�b�v�V�F�A�̓��{��Ƃ��A��N�A�H��̔������̂Ő��Y�s�\�Ɋׂ����B�H��̑����ғ������߂���O�̃��[�U�[�̐��ɑ��āA���Ђ̐ӔC�҂́u���܂藘�v�̏o�鏤���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���̂ŁA�����̓���������v�Ɠ����āA���̂Ђキ�����B���̐^���𖾂����ƁA�ߓ��Ȓl���������œ��O�̋������[�J�[��P�ނɒǂ�������̂͗ǂ����A������̎Z�̎��Ȃ������ɐ��艺�������̂��B
�@�Q�P���I���}���������A��ʐ��Y�̎���͏I������Ƃ����邪�A�H�Ɛ�i�������ڎw���A�W�A���́A������J���Ɓu�㔭�����v�v�����ėʎY�E���l�����ɏo�Ă���B���Ă͓��ĊԂȂǂŋƊE�����̈ێ����b������ꂽ���Ƃ����������A���ł͂����]�ނ��Ƃ�����Ȃ��Ă���B
�@�n�C�e�N�Y�Ƃ͂悭�u�n�C�e�N�n�R�v�Ƃ������t�����s�I�Ɏg����悤�ɁA�Z�p�v�V�̐��ʂ̕\��Ƃ��ĉ��i�j�i�ށB�c�q�`�l�̉��i������̂�������킸�R�h�����x�Ɏ��ʁi���イ���j����Ƃ����u�����[���v�͂��̂����Ⴞ���A�L���i�j���P�O�O�O�j�r�b�g����Ȃ炢���m�炸�A���K�i�l���P�O�O���j�r�b�g����ɂ܂œK�p�����Ƃ���Ζ��ł���B
�@�Z�p�v�V�ɂ�萻�i���i�������闘�_�͕]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�߂�����͋y���邪���Ƃ��ŁA�Z�p�J���ւ̃C���Z���e�B�u��n�C�e�N�s��ւ̎Q���ӗ~�����ނ����Ă��܂��Ă͌����q���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�i�Q�O�O�R�^�O�W�^�Q�T�j
�@�y�J�^�J�i�p��̔×��z�@
�@�@�ŋ߁A�O��������̂܂܃J�^�J�i�ɒu���������u�J�^�J�i��v�̔×������ɂȂ��Ă���B���ہA�茳�ɂ��鎩���ԊW�̖{���J���ƁA�u���`���₷�����[�t�T�C�h���[���̃A�E�^�[��������̃t�����g�T�C�h�����o�[�ɁD�D�D�v�A�Ƃ������ꕶ������B���̎�̃J�^�J�i�q��́A�Ԃ̐��Ƃ�}�j�A�Ȃ炢���m�炸�A��ʂ̓ǎ҂ɂ͂قƂ�Ǘ����̋y�Ȃ��Ƃ���ł��낤�B
�@�@��ʏ��ł���������A��发�ƂȂ�Ɛ����Ēm��ׂ��B��[�Z�p�̈�p���߂�l�H�����̖{���J���ƁA�E�F�b�g�E�F�A�A�Z�����[�I�[�g�}�g���A�A�u�_�N�V�����Ƃ������p�ꂪ���X�Ɠo�ꂷ��B����ł͓��{���Ƃ����`��������Ă��Ă��A�����I�ɂ͉p���ŏ�����Ă���̂Ƒ哯���قł���B
�@�@���̂悤�ȃJ�^�J�i�p��×��̔w�i�ɂ́A�O����̖��ᔻ�Ȏ�e�Ƃ�����肪����͂��Ȃ����B�Ȋw�Z�p���͂��߂Ƃ��������̊w��͉��Ĕ��̂��̂ŁA���ꂪ�p����܂߂Ă��̂܂ܓ��{�Ɉړ������B�V�K�̗p�ꂪ����Ζ{���Ȃ���{��ւ̒u��������Ƃ��i�߂��A���̍H�w��Z�p�̙i�����Ⴍ�j���i�ނ͂����B�Ƃ��낪�A���Ɠ��m�ŕ�����悢�A�������̕����X�}�[�g�ł��������肪�����A�Ƃ��������Ղ��ƑP�I�ȍl�����ŁA�J�^�J�i��̂܂ܒʗp���Ă��܂��̂��B
�@�@�U��Ԃ��āA�]�˒����Ɂu��̐V���v�̖|��ɂ����������c������́A�a�����T�ȂǓ��肷�邷�ׂ��Ȃ��A�͂��߂̂����́u�V���l���i�����_�j�v�ȂǂƂ������ۓI�ȗp��ɏo���킷�Ɠr���ɕ�ꂽ�B���ꂪ�P�N���o�����Ɂu�P���ɂP�O�s���D�D�D�i�ʂ̘J��Ȃ���������₤�ɂ��Ȃ肽��v�ƒ[��i�����j���ׂ��炴��|��\�͂�̓�����B
�@�@�Ȋw�j�Ƃ̑���z��Y���ɂ��A�������̉Ȋw�Z�p�p��̂U�T���͓��{�����������B���̎��g�݂ɓ��{�l�̉Ȋw�Z�p�\�͂ƃA�C�f���e�B�e�B�i��̐��j��ǂݎ�邱�Ƃ��ł��邪�A�����ł͂��ꂪ���ނւ̓r��H���Ă���ƌ������ƂȂ̂��B
�i�Q�O�O�R�^�O�U�^�Q�T�j
�y�͕�ƓƑn�z
�@���̑�w����A�����w���̓����w�N�Ɏ��R�C�i��R�c���ꂪ�����B�Ȃ��ł����l�Ō���Ƃ̎��R�́A�w���ŏ㉉���ꂽ�ꖋ���̂̏����Y�ȁu�Y�ꂽ�̕��v���D�]����Ȃǂ��āA�������S�˂Ԃ�����Ă����B���N�͂��̎��R�̖v��Q�O���N�ɂȂ�Ƃ����B�Ό��l��҂����A�Ƃ��������̗���͑������̂��B
�@ ���R�ɂ͚ʗ_�J�ȁi����ق��ւ�j���������A���N�O�ɏo�ł��ꂽ�c�V��璘�u���l���R�C�i�`�v�i���|�t�H�j��ǂނƁA�u�}�b�`�C����̂܊C�ɖ��[���g�̂�قǂ̑c���͂����v�Ƃ����ނ̑�\��ɂ͎��͖{�̂������āA�x�V�ԉ��j�́u��{�̃}�b�`������Ό͖��v�Ƃ�����̓���ƌ��߂����Ă���B�c�V���͕ʂ̋@��ɂ��A���R�́u�킪�V�g�Ȃ����m��ʏ����������ďɉ��k���A��v���o�l�̐����O�S�̋傩��̙��ށi�Ђ傤���j���Ǝw�E���Ă���B
�@ ���w��i��G��Ȃǂ̑n�슈���ł́A�˂ɃI���W�i���e�B�[�������B���������Έ�̍�i�Ƃ��Č|�p�I�ȉ��l��F�߂��Ȃ����A���Əꍇ�ɂ���Ă͒��쌠�@�ɂ���ĐӔC������B���ꂾ���ɑ��l�̍�i���͕킩�ǂ����͌y�X�ɘ_����ׂ��łȂ��B
�@�͕�Ƃ����A��۔h�̑�\�I��ƃG�h�E�@�[���E�}�l�̖���u����̒��H�v���A�P�U���I�̍�i�ł���W�����W���[�l��u�c���̑t�y�v��}���J���g�j�I�E���C�����f�B��u�p���X�̐R���v�̍\�}�ɂ�������Ƃ̌���������B�m���ɁA�R�l�̒j���������ɂ��ꍇ���悤�ɋY��Ă���p�́A�����w�E����Ă��d���Ȃ��قǎ��Ă���B
�@����ł́A���R��}�l�̍�i�́A��l�̒P�Ȃ�͕�E���ށi�Ђ傤���j���Ƃ����Ό����Ă����ł͂Ȃ��B������̏ꍇ���A�\���҂Ƃ��Ă̊����̂Ђ�߂�����I�[�����Ɉ��A�|�p��i�Ƃ��čL���F�m����Ă���̂ł���B�O�L�}�l�̍�i����N�A���l��Z�U���k�A�s�J�\��̍�i�̉��n�ɂȂ����̂��A��̌|�p��i�Ƃ��Ă��ꂾ�������x�������A�i���͂���������